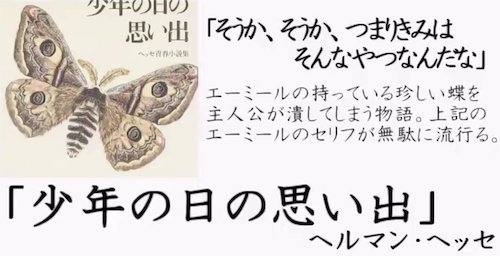(3,300文字)
1947年から現在まで70年以上に渡って国語の教科書に掲載され続けている、日本でもっとも多く読まれた外国文学であるヘッセの短編「少年の日の思い出」。思い出は思い出でも屈辱的でみじめな思い出である。
このコラムでは、「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな。」と同級生に言われて傷ついた12歳の少年の胸の痛むエピソードを追体験し、合わせてこの短編が日本でしか知られていない理由を紹介する。今からちょうど90年前に、訳者の高橋がスイスのヘッセを訪問したときのタイミングにその秘密があった。
息子の2020年度の中学1年生の教科書にも載っていましたが、わたし自身は40年前の記憶がありません。
2021年度の中1の教科書にもありますよ!
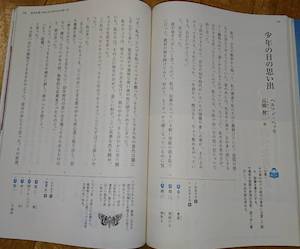
「少年の日の思い出」
作品の位置付け
(訳者の)高橋は、「少年の日の思い出」について、「ヘッセの得意中の得意、彼のお家芸とも言ふべき少年物の典型的な作品である」と述べ、「彼の力作『車輪の下』や『デミアン』の縮図を見る思ひがする。一小品ではあるが、珠玉の作と言ひ得るであらう」と評価が高い。
金沢大学歴史言語文化学系論集第6号(2014)より
あらすじ
全文読みたい方は、教科書を開いて丸ごと朗読してくれているYoutubeがこちらにある。
(27分のうちの最初の20分。ゆっくり読むと結構長い。)
●主人公の少年は、8,9歳頃から、当時流行っていた蝶集めを始め、10歳のときにはそのとりこになっていた。
●家が貧しく立派な標本箱など買ってもらえず、段ボール箱に獲物を飾っていたので、その宝物は仲間に見せなかった。
●しかし、珍しい蝶をつかまえたので、そのときばかりは、近所に住んでいるエーミール(教師の息子で裕福で生意気)に見せずにはいられなかった。
●それを見たエーミールは、展翅(てんし)のやり方などにケチをつけて主人公をバカにしたので、せっかくの喜びが消えてしまった主人公は、二度とエーミールに自分の宝物は見せないと心に決めた。
●それから2年後、12歳の「大きな少年」になった主人公だったが、蝶への熱情は絶頂にあった。ある日、本でしか見たことのない幻の蝶を、例の宿敵エーミールが手に入れたと聞いて複雑な気持ちになりながらも興奮する。
●一刻も早く一目その蝶を見たくて、エーミールの家に行ったところ誰もおらず、ドアが開いていたのでエーミールの部屋まで行ってみたらその蝶の標本があった!
●この蝶の四つの斑点が、挿し絵で見たのよりずっと美しく夢見心地になった主人公は、展翅板から蝶をそっと取り外して自分の手にのせ、そのまま部屋から出てしまった。
●女中とすれちがって我に返った主人公は、慌てて蝶をポケットにねじこみ、元の場所に返そうとエーミールの部屋に戻った。
●ポケットから取り出した蝶はつぶれていた。その蝶をエーミールの机の上に置いて逃げ帰り、母親に自分がしたことを打ち明けた。
●母に、エーミールに謝りに行くように言われ、渋々、エーミールの家に行くと、すでに帰宅していたエーミールが出てきて、だれかに蝶をだいなしにされてしまった、猫の仕業かもしれないと言った。
●主人公はそれは自分がやったのだと言った。もっと詳しく説明したかったが聞いてもらえなかった。
〜ここからのクライマックス、原文引用〜
エーミールは、激したり、僕をどなりつけたりなどはしないで、低く「ちぇっ。」と舌を鳴らし、しばらくじっと僕を見つめていたが、それから、
「そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな。」と言った。
(中略)
エーミールは、冷然と、正義を盾に、あなどるように僕の前に立っていた。彼はののしりさえしなかった。ただ僕を眺めて、軽蔑していた。
●主人公は、自分のおもちゃを全部やる、今まで収集した蝶を全部やると言ったが、エーミールはいらないと言った。
●後悔と恥と絶望で失意のどん底に突き落とされて自宅に戻った主人公は、自分の収集箱を取り出し、今まで収集した宝物の蝶をすべて指で粉々に押しつぶしてしまった。(完)

もっと詳しく知りたい方はウィキペディアに「少年の日の思い出」の項目もありますが、それよりも上の20分の朗読を聞くのがお勧めです。
そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな
70数年前から国語の教科書に載っているこの話を、最近の(平成生まれの)人たちは「トラウマレベルなので、子どもの教科書に載せるのはいかがなものか」などと言ったりもしているが、”キレられるよりもつらい”このセリフが印象に残っている中高生が、全国に多数いるようだ。
エーミールの『そうか、そうか、つまり君はそんなやつなんだな』ってセリフは、しばらくクラスの流行語になってました。クラスのみんなで読めば少しは笑い話にできますけど、そうじゃなかったら精神的にキツいストーリーだと思います。
出典
(高1男子/10代)
このセリフが流行したことを物語るこんなバッグやTシャツも見つけました。(お買い求めはTシャツトリニティさんまで!)


ヘッセと訳者高橋の90年前の実話
日本語でしか読めない「少年の日の思い出」
日本でこれほど有名な話を、本家本元のドイツ語圏の人たちが知らないという摩訶不思議な事実には、以下の経緯がある。
かなり深掘りしたので、ウィキペディアより詳しくなりました! (三日後には忘れていると思いますが。)
●「少年の日の思い出 (Jugendgedenken)」は、ヘッセが34歳のとき(1911年)に書いた「クジャクヤママユ(Das Nachtpfauenauge)」を、20年後の1931年に改稿・改題して発表し直した作品。
早速脱線しますが、ヘッセがこの話を34歳のときと54歳のときの二度も作品にしたということから、この思い出がどんなに強烈なものだったかが伺えます。
苦くて辛い記憶というだけでなく、なにかのとりこになって没頭した記憶でもあり、そんな情熱は大人になってからは感じることがなくなってしまったという人も多いですね。
脱線が長くなりましたが話を戻します。
●20年後に再発表したのは1931年8月1日付のドイツの地方新聞で、別刷りの土曜版にまとめて掲載された。
(この事実を2007年に突き止めた人の記録を発見したが、背後にいろいろと確執もありそう・・・。)
●1931年8月5日、ドイツ文学者の高橋(当時28歳)が遠路はるばるスイスまでヘッセを訪ねた際、ヘッセ(54歳)は別れ際に「これはまだ本になっていないものですが、電車内ででもどうぞ読んでください。」と言いながら、数日前の新聞の切り抜きを高橋に渡した。
●ヘッセが高橋に新聞の切り抜きを渡したために、ヘッセの手元には『Jugendgedenken(少年の日の思い出)』が残っていなかった。それでヘッセの死後、膨大な遺品・資料の整理の作業が行われたときにこの作品が発見されることはなかった。
●その結果、ドイツで発行された単行本や全集に収録されているのは、1911年の初稿である『Das Nachtpfauenauge(クジャクヤママユ)』のみである。
ちょうどこの話がドイツの新聞に掲載された数日後に、たまたま高橋氏がヘッセを訪問したというタイミングだったのですね!
ヘッセは日本の木版画より富士山の絵葉書を喜んだ
54歳のヘッセと感激の対面を果たした28歳の高橋は、日本に帰国後ヘッセにお礼の手紙と自分の写したヘッセの写真と共に、日本の木版画と絵葉書を送っている。
それに対してヘッセが高橋に送った返信には、木版画も見事だがそれよりも富士山の絵葉書が気に入ったということで、以下のように書かれていたそうだ。
お送りくだすったものの中でいちばんすばらしいのは私にとっては、雲の上にそびえた富士山の小さい写真です。これは音楽のような魅力を持っています。
なお、高橋が南スイスのモンタニョーラ(Montagnola)という村を訪ねたときヘッセは、引っ越しの真っ最中で高橋が新居への最初のお客だった。長年文通を続けていた3番目の妻と暮らし始めたときのようで、ヘッセは同年、その女性と三度目の結婚をしている。最初の二度の結婚が悲劇だったあとの平和な結婚生活はその後ずっと続いたので、その意味でも高橋にとってこの訪問は特別なものになっただろう。
どうでもいいつぶやきですが
28歳の高橋氏が54歳のヘッセについて「もう五十をいくつか越えたいわば老大家であるが」とか、「五十半ばになっても、彼は精神のことに関すると、やはりむきにはらずにはいられないのである。」などと書いているのを読み、わたしも今年54歳だけど、50歳ってそんなにたいそうなもんじゃないよと思ってしまいました。
66歳の私も同感です。先人の義母や母などを見ても同じように感じます。
ノーベル賞作家にしろ、永遠に人間って途上のような気がします。
■参考:ヘッセの「春の嵐」(新潮文庫)内、高橋健二による解説。